| ロータリの綱領 |
 ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、
特に次の各項を鼓吹育成することにある。
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、
特に次の各項を鼓吹育成することにある。第1; 奉仕の機会として知り合いを広めること。 第2; 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。 あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという 認識を深めること。各自が、業務を通じて社会に奉仕するために、 その業務を品位あらしめること。 第3; ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に 常に奉仕の理想を適用すること。 第4; 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交に よって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。 |
|
|
| 4つのテスト:言行はこれに照らしてから |

1真実かどうか 2みんなに公平か 3好意と友情を深めるか 4みんなのためになるかどうか |
|
|
| ◆ ロータリの誕生とその成長 |
 今から約100年前、1905年当時のアメリカは経済恐慌で人心はすさみ、
犯罪は巷にみちているというありさまでした。
これを憂えたシカゴの一青年弁護士ポールP.ハリスは、よい社会をつくるためには、
人の和を図り、世の中に奉仕する気持ちを多くの人が持つようになることが大切だと考え、
ポール・ハリス自身それ以前数年間、想を練り、まず石炭商シルベスター・シール、
鉱山技師ガスターバス・ローア、洋服商ハイラム・ショーレーの3人の友人と語らい、
2月23日、この理想をひろく人々に呼びかけるための第1回の会合を持つに至りました。
今から約100年前、1905年当時のアメリカは経済恐慌で人心はすさみ、
犯罪は巷にみちているというありさまでした。
これを憂えたシカゴの一青年弁護士ポールP.ハリスは、よい社会をつくるためには、
人の和を図り、世の中に奉仕する気持ちを多くの人が持つようになることが大切だと考え、
ポール・ハリス自身それ以前数年間、想を練り、まず石炭商シルベスター・シール、
鉱山技師ガスターバス・ローア、洋服商ハイラム・ショーレーの3人の友人と語らい、
2月23日、この理想をひろく人々に呼びかけるための第1回の会合を持つに至りました。
はじめ数ヶ月は非公式にブースター・クラブ(ブースターとは向上させるの意)と呼んでいましたが、 さらに印刷業界のハリー・ラッグルズをはじめ、他の友人が加わってロータリー・クラブの誕生となりました。 ロータリーとは、集会を順番に、会員が各自の事務所で持ち回って開くことから名付けられました。 この理想は着々と実現され、1908年に2番目のクラブがサンフランシスコにつくられ、1910年には国内クラブ数16を 数えるまでになり、さらに国境を越えてカナダ、英国へと国際的ひろがりをもって発展し, ここにロータリ ー国際連合会ができ、1922年には国際ロータリーと呼ばれることになったのです。 こうして、このささやかな理想の芽生えは、4月末現在159の国家にひろめられて、 1997年12月末現在、地区数521、クラブ数28,531、会員総数は1,193,376名になりました。 |
|
|
| ◆日本のロータリの歩み◆ |
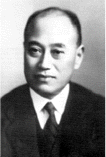 日本のロータリー・クラブは、1920年(大正9年)10月、その項の三井銀行重役米山梅吉氏が、
国際ロータリーから委任されて、東京に設立したのがはじまりで、世界で855番目のクラブでありました。
つづいて1922年大阪、次に神戸、名古屋、京都、横浜に、また当時日本の統治下にあった朝鮮、台湾、
さらに満州国にも設立され、昭和15年には48クラブ、2,000名の会員を数えるまでになりました。
ところが太平洋戦争直前の昭和15年には国際団体に対する圧迫がロータリーにも及び、
ついに日本のロータリーは国際ロータリーから一時脱退しなければならなくなりました。
しかし戦時下にあってもその精神と組織は失われず、例会はつづけられ、戦後の平和回復とともに、
国際復帰をめざす努力が実って、1949年(昭和24年)3月、東京、大阪をはじめ7つのクラブが
国際ロータリー復帰を認められました。
日本のロータリー・クラブは、1920年(大正9年)10月、その項の三井銀行重役米山梅吉氏が、
国際ロータリーから委任されて、東京に設立したのがはじまりで、世界で855番目のクラブでありました。
つづいて1922年大阪、次に神戸、名古屋、京都、横浜に、また当時日本の統治下にあった朝鮮、台湾、
さらに満州国にも設立され、昭和15年には48クラブ、2,000名の会員を数えるまでになりました。
ところが太平洋戦争直前の昭和15年には国際団体に対する圧迫がロータリーにも及び、
ついに日本のロータリーは国際ロータリーから一時脱退しなければならなくなりました。
しかし戦時下にあってもその精神と組織は失われず、例会はつづけられ、戦後の平和回復とともに、
国際復帰をめざす努力が実って、1949年(昭和24年)3月、東京、大阪をはじめ7つのクラブが
国際ロータリー復帰を認められました。
以来めざましい進展をつづけ、北は稚内、南は沖縄、サイパン、グァム、ミクロネシア、マリアナまで、 実にクラブ数は2,200 を超え会員数も約130,000名におよび、現在なお、日本のすべての都市、すべての町に クラブができるように努力がつづけられています。これはすべての会員が、住みよい世の中をめざして、 ロータリーの奉仕の理想をひろめようとの、強い願いのあらわれにほかなりません。現在日本の会員数は アメリカに次いで世界第2位であり、ロータリー財団への寄付額もトップレベルで、大きな貢献を果たしています。 |
|
|
| ◆ロータリーの目的とサービス ◆ |
|
ロータリーでは、社会生活における成功と幸福は、他人に対する思いやりと他人を助けることにあるとして、各自の職業を通じての「奉仕の理想」を目的としております。
そのためには、 1.広く知り合いを求めて奉仕の機会を多く持つ 2.各自の職業に誇りをもってその道徳的規準を高める 3.公私の別なく奉仕の理想を実行する 4.理解と友情を国際的にも広める 、という4つの道を掲げております。 さらにそのための自分の行動は、 1.真実かどうか 2.みんなのために公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか という”四つのテスト”に照らすように決められています。 これは、人のために世のために、奉仕することによって得る利益と楽しさを表したものです。 したがってサービスにも、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の4部門があり、国際間の留学生交換、児童や青少年の保護養成、身体障害者、天災飢餓に悩む人々、そのほか各種の一般社会施設等への援助を行います。 また、自分や他人との職業上の相互関係も円満にして、共存共栄を促進させる努力をつづけております。 そのための話しあい、すなわちクラブ例会には必ず出席して、クラブ運営や相互親睦を図るクラブ奉仕を怠ってはならないことになります。 |